それから三週間後後——
陽光が射し込む昼下がり、ギルドにある彩飾師セナの“彩の間”では、静かな打ち合わせが続いていた。
深緑の法衣を纏った年配の司祭が、彩色が施された《蒼い満月の伝承録》の下絵を手に取り、目を細めている。
「……これは、見事なものですな」
司祭は心から感嘆の声を漏らした。
「前回の“蒼”に徹した世界観も美しゅうございましたが……
今回はまた、印象がまるで違う。
柔らかな黄や、濃緑の木立、光の粒が降る夜の庭園、そして……この、白い小道。
幻想のようでありながら、どこか、懐かしさすら感じます」
私は微笑みながら、静かにうなずいた。
「ありがとうございます。
前の案は、きっと“伝承”という言葉にとらわれすぎていたんだと思います。
今回は、感じたままを描きました。私自身の思い出を、少しだけ、重ねながら」
司祭はその言葉に少し頷き、ふむと口元に指を添える。
「ただ、願わくば——少しばかり、“祈り”や“神性”といった印象も、もう一筆、添えていただけたらと思いましてな。
やはりこれは、信仰を伝える文書でございますから」
いつものことだった。
どんな案を出しても、司祭は必ずどこかに“完璧”を求めようとする。
「……お言葉ですが、司祭様」
控えめに前置きしながらも、まっすぐ相手を見た。
「“思い出づる国”というのは、訪れた人の心のかたち、願いのイメージが具現化される世界だと、私は思っています。
誰にとっても唯一無二で、まったく異なる光景になるでしょう」
”実際に見てきたから”と言っても、さすがに信じてもらえないだろうけど。
「ふむ……」
「ですから——もし、どんな絵を見ても、どこかに空白や欠落を感じられるのだとすれば……
それは、司祭様ご自身の心が、満たされない何かを抱えているのではないでしょうか?」
そう言いながら、(しまった)と胸の奥が冷たくなるのを感じた。
言いすぎたかもしれない。相手は国の教会に属する高位の司祭だ。
もっと言葉を選ぶべきだったか。
だが——
司祭は、呆けたようにじっとこちらを見つめたまま、しばらく何も言わなかった。
睨んでいるのでも、怒っているでもない。ただ、目の奥が深く、何かを探るようだった。
やがて彼は、長く息を吐くようにして、ぽつりと呟いた。
「……ああ。そうか、そうなのかもしれない」
思いがけず返ってきたのは、柔らかく、まるで独白のような言葉。
私は驚きと戸惑いを覚えながら、「あの—」と声をかける。
すると司祭は、我に返ったように軽く両手を上げた。
「いや、失敬。つい、考え込んでしまいました。
お恥ずかしながら、あなたの言葉に、胸を衝かれましてな。
……私はこれまで“絵”というものを、教義や象徴としてしか見てこなかった。
だが今、あなたの絵を前にして――
私は、自分の内側にこそ空白があるのだと、気づかされたのですよ」
司祭は苦笑を浮かべ、年輪の刻まれた指で、目の前の彩色下絵をそっと撫でた。
「……あなたの絵は、まさしく“思い出づる国”そのものです。
美しいというだけではない。見る者に、自らを映す鏡を与える。
それは、信仰と深く通じるものでしょう」
深々と頷きながら、司祭は続けた。
「いやはや、感服いたしました。
我が国の書物工芸ギルドは、実に優れた彩飾師をお持ちだ。
あなたのような方がいて、心強いかぎりですよ」
少し照れくさくなって、笑いながら深く頭を下げた。
“描く”ということは、誰かの記憶や願いと、心で向き合うこと。
その意味を、今の自分なら少しだけ分かる気がした。
打ち合わせが終わり、司祭を見送ったあと。
静かに窓を開け、深く息を吸い込んだ。
外の空気は冷たかったが、どこか澄んでいて心地よい。
夕暮れがゆっくりと深まる空には、淡く光る星がひとつ、またひとつと浮かびはじめている。
ふと目をやると、作業机の端に置かれた黒いリボンが目に入った。
それは、かけがえのない記憶に繋がる、大切なひと欠片。
思い出づる国の、不思議で優しい光景。
最後に見たスーの笑顔。
「バイバイ、セナ。——だいすき!」
あの声も、あの姿も、胸の奥にちゃんと残っている。
けれど、いまの私の頬に涙はなかった。
描くことで、私はあの日と、今を繋げている。
もう会えなくても、もう触れられなくても。
スーと過ごした時間は、今もこうして、ここにある。
「——ずっと一緒だからね、スー」
その声は、夕闇に溶ける風とともに、空へ舞い上がっていった。
どこまでも静かで、どこまでも優しい余韻だけを残して。

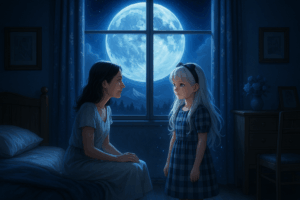
コメント