カーテン越しに、淡く揺れる光が差し込んでいた。
東の空はうっすらと朱を帯び、夜の帳を押しのけるように、朝が静かに近づいている。
(……夢、だったのかな)
ゆっくりと身を起こし、ぼんやりと窓を見つめた。
胸の奥にはまだ熱が残っている。
あれはただの夢じゃない。そんな気がしてならなかった。
ふと、手に何かを握っていることに気づく。
掌を開くと、そこには—— スーに贈った、あの首輪のリボン。
「……やっぱり、夢じゃない」
ぽつりと呟き、リボンを胸に抱いた。
スーと再会した夜。
あの蒼く輝く満月、幻想に染まった町、静けさに満ちた石畳の道。
ふたりで歩き、語り合い、笑い、泣いた夜。
すべてが、今も鮮明に焼きついている。
(描きたい。スーと過ごしたあの景色を、あの時間を、わたしの手で……)
衝動のような想いが、胸を突き上げた。
ベッドから飛び降り、カーテンをさっと開ける。
淡い朝の光が部屋に差し込み、その光のなかで、机の上にスケッチブックを広げ、ペンを取った。
紙の上に、記憶の中の風景をなぞっていく。
蒼い光を纏った町並み、宝石のように輝く石畳、雪山にかかるオーロラのカーテン——
滑らかにペン先が動き、細部を追うたびに、心が落ち着いていく。
(……だけど、これだけじゃ足りない)
線画だけでは、あの蒼の深さも、光の揺らめきも、映しきれない。
(“彩の間”なら……あそこなら、きっと)
ギルドにある、色と光と空気を封じ込めるように仕立てられた、創作のための聖域。
いてもたってもいられず、机を離れてクローゼットから服を選んで着替え始めた。
今はまだ七時前。九時発の列車に乗れば、昼過ぎにはギルドに着ける。
着替えを済ませ、コートを羽織り、カバンに荷物を詰め込む。
最後に、スケッチブックと黒いリボンもそっとしまいこんだ。
玄関に向かう途中、リビングからパンを焼く匂いが漂ってくる。
両親はすでに起きてリビングにいた。
エルヴァンはソファに腰かけ、メガネをかけて仕事道具のチェックをしている。
リゼットはキッチンで朝食の準備をしていた。
「あら、おはよう。どうしたの? どこか出るの?」
リゼットが驚いたように振り返る。
「うん。九時発の列車で、ギルドに戻るよ。ごめんね、突然」
きっぱりと言った。
「もう大丈夫だから。どうしても、やりたいことがあるの」
エルヴァンが顔を上げ、眼鏡の奥で目を細める。
「何か、あったのか?」
少しだけ迷って、微笑んだ。
「スーにね、会ったんだ。元気をもらったの。今度ゆっくり話すよ」
言葉の意味を深く問うことなく、両親はそっと頷く。
「朝ごはん、どうする?」
リゼットの問いに、にっと笑って答えた。
「パンだけ、もらってく。列車のなかで食べるよ」
葡萄パンを紙に包み、バッグに詰め、玄関へ向かう。
ドアノブに手をかけたとき、振り返って、もう一度両親の顔を見た。
「また、すぐ帰ってくるね。その時、ちゃんと話すから」
そう言い残して、急いで家を出た。
木製の扉が閉まる音が静かに響く。
残されたふたりは、目を合わせて、同時に肩をすくめた。
「……切り替えの早いところは、あなたにそっくりね」
リゼットが呆れたように笑う。
「いや、のめり込むと周りが見えなくなるところは、君にそっくりだと思うけど」
エルヴァンも苦笑しながらメガネを外した。
*
蒸気列車の汽笛が、朝の空気を切り裂く。
駅の窓口で急いでチケットを購入し、滑り込むようにして列車に乗り込んだ。
座席に身体を預けた瞬間、胸の奥からふつふつと熱が湧き上がってくる。
(帰りたい。はやく……描きたい)
あれほど足取り重く感じていたギルドへの帰路が、今はたまらなく待ち遠しい。
自宅に着くなり、すぐに仕事着へと着替え、スケッチブックを抱えて飛び出す。
向かう先は――ギルドにある、私の”彩の間”。
その足取りは、かつてないほどに軽かった。
フェルマーの執務室を訪れると、中では、いつものように几帳面に整えられた机の上で、彼が資料に目を通していた。
「……おや? セナ・ノルディ。
まだ休暇中のはずじゃなかったか?」
穏やかな口調だったが、その瞳には、鋭い観察の光が宿っている。
「フェルマーさん、休暇は取りやめます。
……急ぎ仕事に取りかかりたいんです。彩の間の利用を、許可してもらえませんか?」
フェルマーは書類を机に置き、指先を組んで、じっと見つめてきた。
「心配なのは分かる。だが、戻るには早くないか?
その様子だと、もう『見習いに戻りたい』とは言わないようだが」
それでも、一歩前に出て、深く頭を下げた。
「どうしても仕上げたい仕事があります。今あるイメージを、そのまま形にしたいんです。仕事でもあるけど、それ以上に、大事な……今しか描けない絵なので」
頭を上げ、真っ直ぐに向けられたその瞳に、フェルマーはわずかに目を見開いた。
先日見た、あの悲壮感を滲ませた表情は、もはや、そこにはない。
「……分かった、休暇は取り下げよう。彩の間の利用も許可するよ」
「ありがとうございます!」
頭を下げかけたその時、フェルマーは片手を上げて制した。
「ただし——条件がひとつある。
《夜想曲は偽りを歌う》の案件は、君自身が責任をもって対応すること。
受けた依頼は最後まで誠実に向き合う、それが“責任ある彩飾師”の仕事だ」
一人では、どうしても手が回らない。
ならどうすればいいか、もう答えは出ている。
「はい。わかっています」
きっぱりと答える様子に、フェルマーは満足げに頷いた。
「フェルマーさん、今日アリナは、アリナ・トゥレルはギルドに来ていますか?」
「ああ、アリナ・トゥレルなら、今日は来ているはずだよ」
「アリナに、依頼について助言をもらいたいのですが、構いませんか?」
フェルマーはふっと笑みを浮かべた。
「双方が相談の上で納得のいく方針が見つかるのなら、それが最善だ。
何より君は、一人で何でも抱え込みがちだからね」
「……はい。ありがとうございます!」
丁寧に礼を述べ、フェルマーの部屋をあとにした。
スーと過ごした夜。あの景色と想いを絵に描く。
そのためなら、なんだってやってみせる。
フェルマーは閉じたドアをしばらく見つめたあと、小さく独りごちた。
「やれやれ……まったく、あんなに手のかかる弟子だったかな」
けれど、その声はどこか嬉しそうだった。
*
彩の間の長い回廊を抜け、一つの小さな扉の前で足を止めた。
ドアプレートには、柔らかな筆致で《アリナ・トゥレル》と記されている。
彩飾師としては先輩、けれど気さくに話せる友人でもある——
そんな彼女にこそ、今の自分は、頼みたいと思えた。
軽くノックをする。
「はーい、どうぞー!」
明るく間延びした声が返ってきた。
相変わらずの調子に、思わず笑みを浮かべながら扉を開ける。
陽の光がたっぷり差し込む室内。
色見本とスケッチが広がる作業机の前で、くるりと首を回して振り返ったのは
——アリナ・トゥレル。
長身の、すらりとした体型に、柔らかく波打つ淡い金色のミディアムロングヘア。
ラフなシャツワンピースに、エプロンや袖口には絵の具の痕が淡く残っている。
「おお、これはこれは。珍しいお客様だね!」
アリナは驚きとともに、いつもの気取らない笑顔を向けてきた。
ライラックグレーの瞳は、優しげな目元ながら、じっと見つめられると少しドキリとするような、不思議な存在感がある。
「どうしたの? セナが私の部屋に来るなんて、びっくりしたよ」
「……ちょっと、受けている依頼のことで相談したいことがあって」
「へぇ、依頼の相談?」
私が頷くと、アリナは目を輝かせた。
「もちろんいいよ、友の頼みだ。喜んで聞くさ!
少し話す時間くらいあるよ。そこ、座って」
「ありがとう」
勧められるまま、小さな木製の丸椅子に腰を下ろし、スケッチブックを抱え直した。
ひとつ息を整え、静かに口を開く。
「実は、作家のナジュ・イルマという依頼主から《夜想曲は偽りを歌う》っていう新作小説の装飾依頼を受けててね。
下絵を提出したんだけど、差し替えの相談が来てるの。
今、他の案件も重なって手が回らなくなってさ。
少し、手を貸して欲してもらえないかな?」
その瞬間、アリナの目が見開かれる。
「……え、うそ。ナジュ・イルマって、小説家の?
《夜想曲は偽りを歌う》って新作の依頼受けてるの!?
いいなぁ、私、あの作家さん、ファンなの!」
大げさな仕草で胸を押さえるアリナに少し面食らいつつも、肩をすくめた。
「ええっと、できるなら共作という形で、初期デザインだけでも関わってもらえたらと思って。もちろん、アリナが忙しいなら無理は言わないよ」
アリナは目を潤ませながら大げさに答える、
「そんな……初期デザインだけなんて言わず、仕上げまで一緒にやりたいくらいだよ。
他に仕事を抱えてなかったら、担当変更してほしいくらい。
とにかく、ぜひやらせて! うわぁ、楽しみ!」
その姿を見て思わず吹き出すと、アリナも笑った。
「ありがとう、アリナ。本当に助かる」
笑い合うふたりの間に、温かな空気が流れていく。
——こうして、私の再出発は、新たな仲間とともに始まった。
いままで、人に迷惑をかけないようにと、ひとりでこなせなければ一人前じゃないと、そう思い込んで何でも抱え込んできた。
でも、こんなふうに頼ってもいいんだ。
誰かと手を取り合って、もっと素晴らしい世界を生み出していくことだって、きっとできる。
スーは、そのことも教えてくれた。

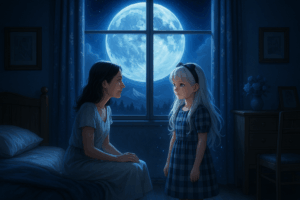
コメント