町は静まり返っていた。
家々の窓には灯りひとつなく、煙突から青いゆらめきだけが立ち上っている。
命の気配は感じられず、まるで演出された幻想のように思えてならなかった。
「誰もいないね」
そうつぶやくと、スーはふんわりと笑って言った。
「そうだよ。だってここは、わたしとセナだけの世界だからね」
「わたしたちだけの、世界……?」
この静寂、この美しさ。この町に、今この瞬間、ふたりしかいないという不思議。
それが恐ろしいのではなく、むしろ、とても心地よかった。
通りに並ぶ街灯は虹のような光をたたえ、足元の石畳をまるで宝石のように照らしている。キラキラと光る石畳の道を、ふたりは手をつないで歩いた。
子どものころに通ったパン屋の角を曲がり、川辺の並木道へ向かう。
「……なんだか、懐かしいね。昔も、こうしてよく歩いたよね」
「うん。わたし、一緒にお散歩するの、大好きだった」
スーは笑いながら、腕にぴとりと寄り添う。
見た目は人の姿だが、仕草は当時のスーそのものだ。
けれど今は、言葉を交わせる分だけ、もっと近く感じる。
「わたしさ……どこ行くにもセナについて行ってたでしょ?
一緒にいたかった、っていうのもあるけど、もうひとつ理由があるの」
「え?」
スーは空を見上げながら、ぽつりと語り出した。
「ほら、前にわたし、迷子になったことがあったよね?……」
目をふっと細め、当時のことを振り返る。
「たしか、私が市場のほうに行って、スーが見えなくなって……」
「あのとき、すごく不安だったの。
知らない匂いがいっぱいで、セナの姿も声もなくて……
どこにいるのか分からなくて、こわくてたまらなかった」
スーは少しだけ声を曇らせた。
「でも、遠くから声が聞こえたの。
『スー!どこ!』って……すごく大きな声だった」
「あの時は慌てたよ。
スーに何かあったんじゃないかって……
不安で仕方なくて、泣きながら探しまわったもん」
「その声が聞こえて、すぐに見つけられたの。
あの時から、決めたんだ。もう側から離れないって」
スーの方を見て、手をそっと握り直す。
「私も……あのときから、ちゃんとスーを見ていようって思ったの。
だから――」
「黒いリボンを、つけてくれたんだよね!」
「そうそう!」
ふたりは同時に声をあげて、顔を見合わせた。
思い出が、まるで宝石のようにふわりと浮かびあがり、笑い声に変わって弾けた。
「リボンをつけたら、スーの白い毛にすごく映えて、可愛かったな」
「あはは、あれ、ちょっとくすぐったかったよ。でも……すごくうれしかった」
スーは満面の笑みを浮かべ、頭を寄せてきた。
ふたりの歩みは、昔と変わらず、のんびりと石畳の上を進んでいく。
石畳に二人の影が揺れて、夜の静けさが足音だけを際立たせている。
ふいに、スーが立ち止まった。
振り返った瞳は、さっきまでの笑みを失い、深い湖のように沈んで見える。
「……ねぇ、セナ」
風にかき消されそうなほど小さな声。
「どうしたの?」
スーは答えず、しばらく空を見上げていた。
雲の切れ間から満月が覗き、その蒼い光が頬をなぞる。
やがて、ためらうように口を開いた。
「……その、ずっと、聞きたかったことがあるの」
胸の奥で、何かが小さく軋んだ。
その声には、やさしさと、痛みが同居していたから。
「わたしが、もう動けなくなった頃、さ……
わたしのこと、負担になってた?」
呼吸が一瞬止まった。
思わず笑ってごまかそうとしたが、喉がうまく動かない。
「スー、そんなわけ——」
「あの頃……あんまり一緒にいてくれなかったよね」
スーの頬を、光るものが滑り落ちる。
「寂しかったし……怖かった。動けなくなったわたしは、負担だったんじゃないかって。
だからね……最後の時、セナがいなくて、少し安心したんだ。
元気だった頃の私を、覚えていてほしかったから」
あの日々が、胸の奥で鈍く疼く。
ギルドに通い始めた私は、必死で未来を掴もうとしていた。
その手を伸ばす間、スーの温もりを…どれだけ、置き去りにしただろう。
「……負担になんて、一度も思ったことないよ」
声が震える。
「ただ、必死だっただけで……」
そこから先の言葉が出てこなかった。何を言っても、言い訳にしかならない。
沈黙が落ち、蒼い光だけが二人を包み、石畳の影は長く伸びていく。
スーは涙を拭い、夜空を見上げた。
「……ここで一緒にいられるのは、夜明けまでみたい」
その言葉が胸に落ちるまで、時間がかかった。
「夜明けまで……?」
「うん。夜が明けたら、本当にお別れ。……たぶん、そう」
心臓が不規則に跳ねる。
穏やかで温もりのある今が、砂のように指の間から零れ落ちていく未来が、もう見えてしまった。
スーはかすかに笑った。
「だから、最後まで笑っていたいの」
その笑顔が痛くて、泣きたいのに泣けなかった。
スーがそっと手を差し出す。小さくて、あたたかい手。
「……まだ時間はあるよ。一緒に歩こう」
私はその手を握り返し、二人は再び歩き出した――
夜明けという終わりが、確かにそこに迫っていることを知りながら。

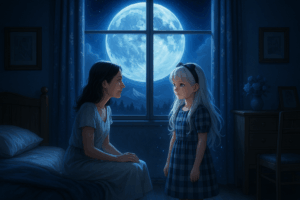
コメント