……誰かが、私を呼んでる?
優しく、耳の奥に響く声。
どこかで、ずっと前に聞いたことがあるような――
懐かしさに胸を掻きむしられるような声だった。
(誰なの……?)
寝ぼけた頭が、その問いに答えを出す前に、声はだんだんとはっきりしてくる。
「……セナ、セナ、ねぇ起きて!」
少女の声――それは確かに、私の名前を呼んでいた。
はっと目を開け、跳ね起きる。
心臓が強く打ち、息が詰まる。
寝ぼけた意識がようやく現実へ戻ろうとしたとき、すぐ隣に――
見知らぬ、小さな女の子がちょこんと座っていた。
年のころは十にも満たないくらい。
雪のように白い髪をツインテールに結い、
透きとおる碧い瞳が、まっすぐにこちらを見つめている。
その顔立ちにも、服装にも、どこか既視感があった。
赤いチェック柄のワンピースに、裾のレース。
――あれは、幼い頃に私がいちばん好きだった服。
「すごいすごい! 本当にセナだ!」
少女ははしゃぐように言うと、勢いよくこちらへ飛びついてきた。
「ちょ、ちょっと……ごめんなさい、あなた誰なの?」
あまりに突然のことに、私は言葉を探しながら、肩をそっと押し離そうとする。
すると、少女はぱちりと瞬きして、にっこりと笑った。
「わたし、スーだよ。……猫のスー。いま、ひとになってるみたい。
どんな姿か、自分では見えないけど」
(……スー?)
その名前が唇に触れた瞬間、胸の奥がかすかに震えた。
「スーって、あの……白猫のスー? 本当に?」
私は混乱したまま、少女の顔を見つめる。
どこか現実感のない、淡い光に満ちた空間。
ここは、私の部屋のはず。でも、何かが違う。
壁も、床も、天井も。すべてが夜の帳のなかで、かすかに光っている。
カーテン越しに差し込むのは、月の蒼い光。
まるで、夢と現が交わる境界のような、幻想的な空間だった。
(まさか……でも、本当に――)
私は改めて、少女の姿をじっと見つめた。
その髪型も、ワンピースの模様も、懐かしすぎて涙が出そうになる。
首元ある、小さな黒いリボン。それは、私が昔スーに迷子にならないようにと、つけたことのある飾りに、そっくりだった。
少女は、きょとんとした様子で小首をかしげて、こちらを見返した。
見た目は違うけど、昔スーが首をかしげて不思議そうにこちらを見返すしぐさと重なる。
(この首を傾けるしぐさ……)
「……スー、本当に、スーなのね!」
私は胸の奥から込み上げてくる感情に耐えきれず、少女の体を強く抱きしめた。
白い髪が頬に触れる。細くて軽い肩。
だけど確かに、そこに「スー」がいる――。
「会いたかった……ずっと、会いたかったよ……」
私はそうつぶやきながら、腕のなかのぬくもりに、ただただ震えた。
少女――スーは、そっと背中に手を回して、くすくすと笑った。
「わたしも。ずっと、会いたかった」
*
少し身体を離し、お互いの姿を確認する。
改めて見ても、髪と瞳の色以外は、幼い頃の私と同じ姿をしている。
「今のスーは、小さい頃の私とそっくりな姿をしてるよ」
その言葉に、少女は満面の笑みを浮かべる。
白くやわらかな髪がふわりと揺れて、澄んだ碧い瞳が真っすぐ見返す。
「セナと一緒? 嬉しい!
ずっと会いたいって、思ってたからかな?
会いたかったんだよ、ずっと……ずっーと、ね」
その言葉に、胸の奥がきゅっと締めつけられる。
生前のスーが、言葉にできないまま伝えたかった想いが、今こうして言葉になって届いている。
「だから……たくさん話したい。たくさん、そばにいたい」
スーは無邪気な笑顔で、恥ずかしげに指を絡めるようにして、私の手を取った。
見た目は幼い頃の自分――でも、中身は確かにあのスーのようだった。
少し戸惑いながらも、その小さな手のぬくもりを確かめるように握り返す。
「……うん、私も。こんなこと、信じられないけど……でももう、疑いようがないよね」
思わず笑いながら、頬に落ちた涙をそっと指で拭った。
「ねえ、外に行こうよ!」
スーが突然、ぱっと顔を輝かせて言った。
「……外?」
「うん、ねぇ行こう。早く!」
そう言うなり、スーは私の手を引いて立ち上がり、部屋の窓辺へと駆け寄る。
「ちょっと待って、玄関からじゃなくて?」
「こっちのほうが早いもん!」
そう言って、迷いもなく窓を開けたスーは、そのまま月光の下へ飛び出した。
「スーっ!?」
思わず叫びかけたその瞬間――
スーは、まるで羽が生えたかのように、ふわりと宙に浮かび、舞い降りるように降りていった。
私の手は、まだスーの手とつながっている。
そのまま引かれるように、一緒に窓から身を投げ出した。
(落ちる……!)
と思ったのは一瞬だけ。
重力の感覚が、まるで別の世界のものになったかのように、ふたりの体はゆっくりと空気を滑り降り、やわらかな足取りで地面へと降り立った。
「……え……?」
私は驚いて視線を上げ、そして言葉を失った。
そこに広がっていたのは――確かに、見慣れた故郷の町。
けれどそれは、かつて一度も見たことのないほど神秘的で、美しい世界だった。
空には蒼い満月が燦然と輝き、凍てつく夜の帳が降りるはずなのに、まるで朝焼けの光を閉じ込めたかのように、鮮やかな色彩に満ちている。
レンガ造りの家々は月光に照らされ、普段は地味に見える煉瓦の一つ一つが、月の魔法にかかったかのように光を宿し、複雑な模様を浮かび上がらせる。
窓は月光を映す鏡のように蒼く光り、窓辺に並ぶゼラニウムの鉢は、映して淡くきらめき、まるで命を得たかのようにそよいでいた。
路傍の花々は青、紫、水色へと色を変え、夜風にそっと揺れながら、まるで月のダンスを舞っているようだ。
気づけば、いつの間にか私の衣服は、彩飾師で働く時の服装になっている。
寒さもまったく感じなかった。
「これが……思い出づる国」
そう呆然とつぶやいた。
この景色は、まるで夢のなか。
でも故郷の町だからか、どこか既視感もある。
いや、夢だとしても、こんなにも鮮やかに心を震わせる夢があるだろうか。
遠くへ目をやると、彼方には雪を頂いた山々が、蒼く輝く稜線を描き、その上空には、淡いオーロラがゆらめいていた。緑と紫が混ざり合う光のカーテンが、静かに、優しく、夜空を彩っている。
「……すごい……キレイ」
思わず声に出すと、スーはにっこり笑って、手を引いた。
「行こう、セナ。歩こう、いっぱい!」
「うん……」
もう何も言えなかった。
ただ、目の前の不思議な少女と手をつなぎながら、懐かしくて初めて見る町のなかを歩き出す。
その手のぬくもりだけは、確かに本物だった。

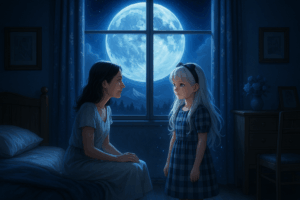
コメント