夜も更け、食後の皿を下げたあと、それぞれ紅茶のカップを手に、暖炉の前に腰を下ろしていた。薪の燃える音だけが、部屋の中にゆるやかなリズムを刻んでいる。
私は、暖炉の火をぼんやりと見つめながら、両親のそばにいた。
母・リゼットは椅子の肘掛けに片肘をついて裁縫の仕事の近況を語り、
父・エルヴァンは窓の外の闇に目をやりながら、時折カップに口をつけていた。
誰も何も聞こうとしなかった。
だからこそ、余計に胸が苦しかった。
何も言わなければ、きっとこのまま何も問わずにいてくれる。
私の両親はそういう人達だ。
でも、それじゃあ、二人を心配させてしまう――
「……あのね、お父さん、お母さん」
静かな声で切り出すと、ふたりはゆっくりと視線を向けた。
膝の上で指を組んだまま、そこから目を上げられずにいた。
「……今ね、ギルドで少し、行き詰まってて」
声は落ち着いていたけれど、心の奥にあった何かが少しずつ込み上げてくるようだった。
「仕事が……嫌になってきたの。
自分が、ちゃんとできてるのか分からなくなって。
彩飾師として、私、向いてないんじゃないかって……」
言葉を選びながら話すうちに、喉が詰まりそうになる。
リゼットがそっと、隣に座って肩に手を添えてくれた。
「このままじゃ、ギルドのみんなや依頼主にも迷惑をかけると思った。
だから……ギルドの上役の人に相談して、しばらく休みをもらったの。
だけど……まだ仕事も残っているのに……」
ぽつぽつとこぼれる言葉は、次第に形を失い、涙と一緒に崩れていった。
「私、逃げてきたの……。
彩飾師になりたいって、ずっと夢だったのに。
ふたりとも、あんなに応援してくれたのに……
それを裏切るようなこと、して……」
もう、堪えられなかった。
「ご、ごめんなさい……
私、必死にがんばった、けど、ダメだったよぉ……」
頬に熱いものが流れるのを感じながら、顔を伏せた。
言葉が涙に変わり、嗚咽が喉を震わせる。
その肩を、リゼットがそっと抱きしめた。
「……私たちは裏切られたなんて、思ってないわよ」
優しい声が、頭の上に落ちる。
「あなたが頑張ってたのは、ちゃんと伝わってた。遠くにいても、それは分かってたわ。
でもね、どれだけ頑張っていても、人はつまずくものよ。つまずいたからって、夢を失ったことにはならないわ」
エルヴァンも、静かにカップを置いてから口を開いた。
「自分で選んでここに戻ってこられたなら、それは正しかったってことだ。逃げたことにはならん。お前は昔から、真面目すぎるからな。心労を重ねてないかって、リゼットとよく話してたんだ」
涙に滲んだ視界の中で、ふたりの表情がぼやけて見えた。
けれどその輪郭から、あたたかさだけは、はっきりと伝わってきた。
「……ありがとう、ごめんなさい」
小さく震える声でそう言った。
両親の言葉に、抱きしめられるような安心を覚えながら、もう少しだけ涙を流した。
*
家族に本音を打ち明け、温かな時間を過ごしたあと、
「少しの間ここで過ごして、今後のことを考えたい」と両親に伝えた。
「それがいいわ。焦らなくていいのよ」と、リゼットは微笑み、肩をそっと撫でてくれた。
やがて暖炉の火も小さくなり、家が夜の静けさに包まれる頃、階段を上がり、懐かしい自室へと戻った。懐かしい木の階段を上り、二階の小部屋の扉を開ける。
そこには、少女時代から使ってきたベッドと机、棚の上には古びたスケッチブックや、壁には幼い頃に描いた拙い白猫の絵がピンで飾ってある。
他にも見習い時代に描いた装飾画の見本たちが、時間の中で静かに眠っていた。
そして部屋の片隅には、あの小さなクッションベッドが――
スーのために用意していた、小さな寝床が、今もそっと置かれていた。
「……あの子がいないだけで、こんなに静かだったっけ」
ぽつりとつぶやき、ため息まじりに寝間着へ着替えると、そっとカーテンを開けた。
そのとき、不意に部屋の中へ蒼い光が差し込んできた。
「……え?」
目を瞬かせながら、窓の外を見やる。
そこには、空の中央に蒼く染まった満月が、ひっそりと浮かんでいた。
雪をいただく山並みの上、透きとおるような蒼い光が静かに降りそそぎ、町全体をやわらかく包み込んでいる。
ただ照らしているだけなのに、どこか言葉にできない、幻想的で胸を震わせるような美しさがあった。
けれど、今は――
どうしても素直に、その光を歓迎する気持ちにはなれない。
(……“蒼い満月の伝承”)
自然と、仕事の案件のことが頭をよぎる。
教会から依頼されている伝承録の彩飾――
蒼い満月にまつわる装飾ページは、まだ手つかずのままだ。
納期は迫っている。
にもかかわらず、ペンを持つどころか、まともに原稿に向き合うことさえできていない。
満月の光に照らされながら、思わず頭の中でその一節を思い浮かべる。
――蒼き満月の夜、この世と神界を隔てる境界は消え、世界が重なる。
願いが神に届けば、「思い出づる国」への扉が開かれる――
「たしか、その国に足を踏み入れた者は、願いが形になる……そんな話だったっけ」
言いながら、自分でも乾いた笑いが漏れた。
願いが形になる――
そんな都合のいい世界があるなら、どれだけ救われただろう。
そっとカーテンを引き、ベッドへと潜り込んだ。
枕に頭を沈めながら、ため息をひとつ。
(せっかく、休みをもらって実家に帰ったのに…… こんな夜に当たるなんて、ほんとツイてない)
それでも、目を閉じた後も、まぶたの裏にはあの蒼い光が、ぼんやりと残っていた。
冷えたシーツに身を包むと、どこか心細さが胸にしみ込んできた。
(……スー)
その名前を、心の中で呼ぶだけで、胸の奥がじんわりと熱くなる。
「スーに、会いたいな……」
天井を見上げたまま、そっと呟いた。
「もし本当に、願いが形になるなら、もう一度会って、
ちゃんと、ありがとうって言いたい。
最後に会えなくて、ごめんねって……言いたい」
胸の奥から、あたたかくも切ない記憶が滲み出す。
スーは、寒い冬の夜、私が布団にもぐりながら手を伸ばすと、そっと手元に近づいてきて、ぴたりと身体を寄せてきた。
あのぬくもりは、今も指先に残っている気がする。
「……会いたいよ、スー」
そう言って目を閉じ、やがて、暖炉の残り火のぬくもりが遠のくように、意識も静かに溶けていく。
夢と現の境が曖昧になっていく中、呼吸はゆるやかになり、眠りの深みへと落ちていった。

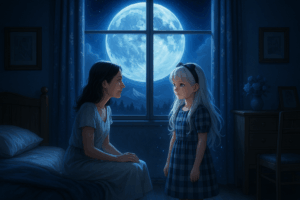
コメント