蒸気を吐きながら、列車が緩やかに減速を始めた。
車輪が軋む音に続いて、窓の外の風景が少しずつ動きを止めていく。
故郷の小さな駅に、ようやく辿り着いたらしい。
ベージュ色のコートの前を軽く合わせ、荷物を抱えて立ち上がった。
扉が開くと、冷たい空気が頬に触れる。王都に比べればずっと澄んでいて、鼻の奥が少しつんとした。けれどそれも、どこか懐かしい痛みだった。
見上げれば、空は広く、淡い灰青の雲がゆっくりと流れている。
駅の構内には人影もまばらで、どこか時間が止まっているような静けさに包まれていた。
自然と街並みがゆるやかに重なりあうようなこの地――私の故郷。
レンガ造の家並みが斜面に沿って立ち並び、遠くには雪をかぶった山並みが霞んでいる。
実家までの道のりは、子どもの頃なら駆けていける距離だ。
だが今は、ゆっくりと景色を確かめるように歩いている。
昔とほとんど変わらない、のどかな町の風景。
たった二年帰っていないだけなのに、なんだか懐かしい。
石畳の路地に、霜に覆われた木の葉。
焼き菓子の香りを漂わせるパン屋の前を通り過ぎる。
ふと、昔飼っていた白猫の面影が、脳裏に浮かんだ。
……かわいい白猫のスー、今はもういない。
私が八歳の時、白い子猫を両親が家に連れてきた。
スースーと寝息を立てて眠る様子から、『スー』と名前を付け、それから家族同然のように一緒に育った。
スーは私にとてもよく懐いて、どこへ行くにも隣にピッタリついてきた。この石畳の路地も二人でよく散歩したものだ。
寒い時にはスーを抱きかかえて一緒に温め合った。
フワフワの綿毛のような毛が、とても心地よかった。
顔を眺めると首をわずかに傾けて、不思議そうにこちらを見返す。
言葉は通じなくても、気持ちは通じ合っている気がした。
でも、あの小さな白猫は、最後の瞬間を看取ってやることさえできなかった。
スーは八歳になると体が弱り始め、もう一緒に出歩くこともできなくなっていた。
だけどいつも私の部屋の隅にある専用のベッドに丸くなっていて、ずっとそこに居てくれるのだと、居てくれるだけでいいと、そう思っていた。
でも、私が十七歳で彩飾師の弟子入りのためギルドに通っていた頃、ある日実家に帰ると、両親からスーは亡くなったと聞かされた。
あの時ほど、悔しくて、悲しかったことはない。
スーのいなくなった部屋で、なぜ最後の時に一緒にいてやれなかったのかと涙を流しながら悔やんだ。
スーがいなくなってもう七年。
心の中で整理をつけたはずだった。
――けれど、なぜか今、胸の奥が騒いで仕方がない。
あの日からずっと、閉ざされていたはずの何かが、扉の向こうでそっと手を伸ばしているような、そんな感覚だった。
家の角を曲がると、見慣れたレンガ造りの家が目に入る。
煙突からはうっすらと白い煙が立ちのぼり、花壇には冬に強い赤紫のヘザーが咲いていた。
庭の片隅には、かつてスーが日向ぼっこをしていた木製ベンチがそのまま残っている。
ノックをする前に、そっとドアノブを回す。鍵は、かかっていなかった。
「……お母さん?」
扉を開けると、部屋の奥からミシンの静かな音が聞こえた。
数秒後、それが止まり、軽い足音とともに姿を現したのは、栗色の髪を後ろで一つに結い、目元にはやわらかな笑い皺。
赤いチェックのワンピースにスモーキーグリーンのエプロンをした女性――
母、リゼットだった。
リゼットは自宅で裁縫師(仕立て屋)をしていて、街の人々の衣類や刺繍入りのハンカチ、小物などを手がけている。今は仕事中だったようだ。
「……セナ?」
驚いた表情のまま、リゼットはしばらく言葉を失っていた。
けれどすぐに、頬をほころばせて駆け寄ってくる。
「どうしたの、急に。手紙もなしに……まあ、元気そうでよかったわ」
「……うん、急に来たくなって」
声はかすれていたが、リゼットはそれを咎めず、抱きしめるように肩を包んだ。
ほんのりとハーブティーのような香りがする。
懐かしくて、胸がきゅっと締めつけられた。
昼下がり、暖炉の火がぱちぱちと音を立てる中、リゼットと並んで淹れた紅茶の香りが部屋に広がっていた。
「しばらく忙しいからって帰ってこなかったから、心配したわ。
ほんと、少し痩せたかしら。ギルドの仕事、大変だった?」
「うん、まあちょっと、いろいろあって。休みをもらったの」
「そう……よく帰ってきてくれたわ」
リゼットの言葉は、それだけだった。
問い詰めたり、無理に明るく振る舞わせたりはしない。
ただ、そう言って微笑んでくれる。それだけで、とても救われる。
その日の夕暮れ。
ギィ……と扉が開く音がして、父・エルヴァンが帰ってきた。
エルヴァンは鍛冶師ギルドで働く熟練の職人で、短く刈った黒髪、整った髭と優しい眼差しが印象的だ。煤けた作業着と革の前掛けを着ていて、腰に巻かれた革製の道具帯に収められているハンマーやペンチが、カチャカチャと音を鳴らしていた。
私の顔を見て目を見開き、次の瞬間、大きい手でぽんと頭を撫でた。
力仕事が多いから、相変わらず筋肉質で分厚い腕をしている。
「おう……帰ってたのか」
「うん、ただいま、お父さん」
エルヴァンは普段から寡黙で、あまり詮索するようなことはしない。
でもそれだけで、すべてが通じたような気がした。
夕食は、野菜と豆のスープに母の焼いたハーブパン。
そして、エルヴァンがせっせとこねて焼き上げた、葡萄パンが食卓の中央に置かれた。
「……懐かしい味」
パンを一口かじると、甘く、やさしい味がした。
エルヴァンが黙ってニッと笑ったのを見て、私はは思わず目を伏せた。
心の奥に積もっていた疲れや寂しさが、少しずつ、溶けていくようだった。
家族という灯火に、少しだけ温められていく自分を感じながら、小さく息を吐いた

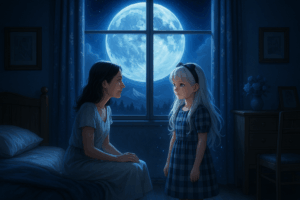
コメント