蒼い満月は、ただ空を照らすだけのものではない――。
その夜、天と地の境はほどけ、世界がひとつになる。
神に願いが届けば「思い出づる《おもいいずる》国」への扉が開き、
そこでは死者と再び会えた者もいれば、天啓を授かった者もいたという。
翼を与えられ、空を駆けた者さえいた。
誰が最初に語ったのかはもうわからない。
それでも、この町では夢のような伝承として今も囁かれている。
そして今、私が手がけているのは、まさにその伝承を綴った一冊だった。
「セナ・ノルディさん、下絵はとてもよかったですよ」
銀糸の刺繍をあしらった深緑の法衣が、司祭の手振りに合わせて揺れる。
「ただ、もっと“厳かに”。でも“親しみやすく”。
蒼い満月が“思い出づる国”を照らす場面は……そうですね、
たとえば“光が差し込む夜”のような――」
彼の言葉を聞きながら、私は無意識に筆を止めていた。
工房の外では、石畳の大通りに真鍮の看板が光っている。
《書物工芸ギルド》――書を作る職人たちが集う、王都でも名の知れたギルドだ。
紙とインクの匂いが満ちるこの場所で、私は祈りや物語に色と模様を与える”彩飾師”として働いている。
二階の奥の小部屋、通称《彩の間》の一室が、私の持ち場になる。
――光が差し込む夜?
司祭の言葉に、私は無意識に筆を止めた。
意味を問われれば……正直、まったく分からない。
机に広げた下絵には、銀の下地に藍と群青を幾重にも重ねた蒼い満月。
私なりに“神聖さ”を込めたつもりだった。
だが返ってきたのは、「イメージと違いますね」のひと言。
「……具体的には、どのような絵をご希望でしょうか?」
困惑を隠しきれず尋ねると、司祭は誇らしげに首をかしげた。
胸元で高位の立場を示す小さな銀のブローチが光る。
「蒼き満月は、この国にとって特別な神話です。その夜にだけ、神と人の世界が重なる。だから“雰囲気”が大事なんですよ。感じるままに、描いていただければ」
――感覚でしか語られない依頼。それが、いちばん難しい。
私は軽く頷き、差し戻された絵の余白に走り書きをする。
『厳かに、親しみやすく。光が差し込む夜のように、蒼い月が照らす様子』
言葉は美しいけれど、曖昧で、少し怖い。
司祭は柔らかな笑みを残し、静かに去っていった。
私は息を吐き、机上の下絵を見つめる。
いつからだろう、自分の絵が“誰かの正解”に削られていくように感じ始めたのは。
*
彩飾師に憧れたのは、まだ子どもの頃だ。
絵本の色彩と光に心を奪われ、物語に魔法をかけるような絵を描きたいと夢見た。
だが現実は早くに理想を飲み込んだ。
司祭、貴族、作家、研究者――依頼主の好みは皆違い、どれも“絶対”だった。
「金色が下品ですね、もっと自然に」
「笑っているようで笑っていない表情で」
「花の数が多すぎます、意味が変わります」
“感じるままに”描いても、“感じ取って”はもらえない。
気づけば、描くこと自体が怖くなっていた。
私は椅子にもたれ、深く息を吐く。
《彩の間》と呼ばれる作業部屋は、一人前にだけ与えられる個室だ。
大きな机、道具棚、顔料の瓶。窓からの自然光が曇り空にやわらぎ、紙と絵具とインクの匂いが静けさに溶けている。
ふと鏡に目をやると、そこに映るのは、ところどころ顔料が付いた無地のシャツの作業服を着た、束ねた黒髪と曇った翡翠色の瞳をしている、冴えない私の姿。
昔は、いろいろな服を選ぶことを楽しんでいたのに、最近は普段着も作業服のままだ。
“努力は裏切らない”と信じ、十七でギルドに入り、五年の下積みを経て一人前になった。
この二年間、迷惑をかけずに働き続けても、結果だけが「違う」と突き返され、積み上げたものは何度も崩れた。
「……私、なんで絵を描いてるんだっけ」
つぶやきは梁に吸い込まれた。
別室では新人たちが、賑やかに一冊を分担して仕上げている。
見習いだった頃の私は、「絵を描くのが好き」と信じられていた。
指示どおりに描くことが多くても、仲間と共に筆を動かす時間は、今よりずっと楽しかったのだ。
椅子から立ち上がると、腰に鈍い重さが残った。
長く座りすぎたせいで、数歩歩いただけで身体がきしむ。
木箱から顔料の瓶を取り出そうとした、そのとき――
――コン、コン。
「はい、どうぞ」
返事と同時に、木の扉が静かに開いた。
「失礼します……少し、よろしいですか?」
顔をのぞかせたのは、依頼管理を担当する青年。
赤茶の短髪に琥珀色の瞳。いつも人懐っこい笑みを浮かべているのに、今日は険しい。
――嫌な予感がする。
「先日お届けした『夜想曲は偽りを歌う』の装飾案ですが……
“納期内にすべての下絵を差し替えたい”との連絡がありました」
指先がわずかに震え、瓶が机を転がる。あわてて受け止めたが、言葉は出ない。
「……すべて差し替え、ですか」
自分でも驚くほど、平坦な声だった。
『差し替え』は『修正』とは全く違う。
下絵ごと入れ替える――つまり、ボツだ。
「はい。“別の彩飾師に切り替える可能性もある”とも」
胸の奥に泡のようなものが湧き上がる。
『夜想曲は偽りを歌う』は、貴族文化を土台にしたミステリー小説だ。
私には縁遠い題材だったが、文献をあさり、装飾や服飾、建築まで調べ、描き切った。
何度も「違う」と突き返されても、食らいついて修正を重ねたのに……。
「……わかりました」
感情の色を欠いた声が、部屋に落ちる。
青年は視線を伏せ、静かに去った。
瓶を棚に戻し、壁にもたれかかる。
足から力が抜け、胸にぽっかりと空白が広がった。
迫る納期、重なる依頼……それでも一番こたえたのは――
――ダメだった。
誰にも責められていない。
それなのに、自分で自分に「もう駄目だ」と告げた気がした。
私の絵は、届かなかった。ただ、それだけ。
けれど、その“たったそれだけ”が、耐えがたいほど重かった。

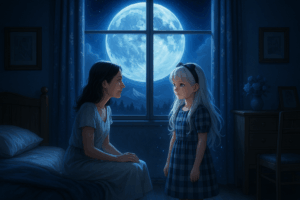
コメント