列車が緩やかな勾配を下るたび、車輪のきしむ音が一定のリズムで耳に響く。
窓辺にもたれながら、流れていく景色をぼんやりと眺めていた。
赤茶けた屋根の家々が遠ざかり、代わりに野原と風車の並ぶ小さな集落が近づいてくる。
そのどれもが懐かしくて、でも今の自分にはどこか遠い。
――昨日のこと、まだ引きずっているのかな。
*
「……見習いに、戻れないでしょうか」
その言葉が口をついて出たとき、自分でも情けないと思った。
でも、それ以外に方法が思いつかなかった。
静かな夕暮れの、ギルドの一室。
書籍が詰め込まれた本棚に、壁にはびっしり書き込まれたスケジュール表、デスクの上には大量の書類が山積みになっている。
私は、ギルドの上役であり、かつて師として一から育ててくれた彩飾師、フェルマー・レイスの前にいた。
金髪に薄い髭のある、深い蒼灰色の瞳をした壮年の男性。
いつものように淡い青灰色の長衣をまとっており、襟元には上級彩飾師である彼の矜持が刺繡されている。
フェルマーは、銀混じりの金髪を指で払いながら、静かに私の言葉を聞いていた。
その瞳には驚きも非難もなく、落ち着いた光だけが宿っている。
「自分は、一人前の彩飾師としては実力不足だと思うんです」
「このままでは、依頼主にも、ギルドにも迷惑をかけてしまいます」
「できることなら……また見習いに戻って、一からやり直したいです」
俯き加減でぽつりぽつりと零れるように、私は言葉を紡いだ。
情けなさと申し訳なさでいっぱいで、涙が溢れるのを必死で我慢した。
フェルマーは黙っていた。
それが否定なのか肯定なのか、わからないまま、私は言葉を続ける。
「《夜想曲は偽りを歌う》の件は、私には荷が重すぎたみたいです。
私なりに、勉強しましたが、結果的には、依頼主の要望には応えられず……」
「ふさわしくなかったかどうか、判断するにはまだ早いさ」
フェルマーの声は低く、しかしどこか温かかった。
「まったく……独り立ちしても、その生真面目でクヨクヨする性格は変わらないな」
フェルマーは、微笑を浮かべながらそう言った。
「お前の仕事は、誠実で、丁寧で、とくにミニアチュール(細密画)の繊細な表現は他の者より抜きん出ている。そこに疑いはない」
私は言葉に詰まる。その一言が、責めよりもずっと重く胸に刺さった。
「……ただな、セナ」
彼は手元のスケッチブックを指先で軽く叩いた。
「依頼主の要望にすべて応えられる人間なんていない。
彩飾師にも、それぞれ“得意と不得意”がある。
時には、依頼そのものを他の彩飾師に任せるという判断が必要なこともある」
「たとえば、《夜想曲は偽りを歌う》の案件なら……
アリナ・トゥレルあたりは引き受けてくれるんじゃないか?」
アリナの名前を聞いた瞬間、私は彼女の笑顔を思い出した。
見習い時代に同じ班で働いていた、明るく快活な彩飾師仲間で、友人でもある。
煌びやかなドレスや宮廷の宴、金糸刺繍の装丁が好きな、絵の華やかさに心躍らせるタイプだ。
確かにあの作品なら、彼女の感性のほうが合っている気がする。
ただ表現が豪奢すぎて修正を依頼されることも多かった気はするが……。
「でも、それじゃあ、アリナの負担が増えてしまいます。
アリナに任せるにしても、私が見習いに戻れば仕事をアシストできるので、納期内に仕上げられるかもしれません。
でも、見習いに戻ったとしても、今私が受けている他の依頼までは《彩の間》の使用を許可していただけますか? なんとか並行して終わらせるので……」
そう口にすると、フェルマーは少しだけ眉をひそめた。
「それだと見習いの仕事も兼任すると言っているようなものだろう。
自分を潰すまで仕事を抱え込むのは、責任ある彩飾師の仕事とは言えない。
“自分を犠牲にして頑張る”のは、美徳じゃないぞ。
……俺は、そんな教え方をしたか?」
淡々とした口調だったけれど、その言葉には、弟子としての私を守ろうとする真剣さがにじんでいた。
見習い時代、フェルマーの指導は厳しかったが、決して無理をさせようとはしなかった。
でも《蒼い満月》の修正に、《夜想曲は偽りを歌う》はすべて差し替え。
どうしたら納期内に終わらせられるのか、検討もつかない。
私は俯きかけて、でも、思わず問い返していた。
「じゃあ私は、どうしたらいいんでしょうか?」
「休め。数日でいい。仕事から離れろ」
即答だった。
「えっ? でも、残っている依頼がありますし、他の彩飾師の方々も忙しいはずで……」
「誰かが休まなければ回らないようなら、それはギルド側の管理の問題だ。
必要なら依頼主に相談するし、いざとなったら、俺も筆をとるさ」
フェルマーの言葉は、静かに、しかしはっきりと響いた。
「……休暇は、お前にとって必要だ。今のお前、ひどく疲れた顔をしているぞ」
その言葉に、私は一瞬、息を呑んだ。
フェルマーは引き出しから書類を取り出すと、立ち上がって私に差し出した。
その書類には、”休暇願”と書かれている。
「命令だ。休め。……何もしなくていい。
しばらく仕事を離れて自分のことだけ考えてみろ。
それで考えが変わらないなら、また話を聞こう」
――私は、黙って書類を受け取った。
*
「ほんと、フェルマー先生は容赦ないなぁ」
窓の外を眺めながら、私はそう独りごちた。
今の状況で休暇と言われても、正直、何をしていいかわからなかった。
でも、気がつけば私は帰郷の切符を手にしていた。
最後に帰省したのは、もう二年前。
私が彩飾師として一人前と認められて、両親へ報告に行った時以来だ。
仕事の忙しさで段々と足が遠のいていたけど、思い出の断片は、今も色濃く胸に残っている。両親が迎えてくれる家と、あの子との思い出が詰まった場所。
……スー。
自然と、その名前が心に浮かんだ。
遠ざかる町と、近づく過去の風景。
風が、ゆっくりとカーテンのように空を撫でていた。
ふと、空を見上げると、雲の切れ間に淡い光が覗いていた。
まだ日は高いはずなのに――それはどこか、蒼さを帯びて見えた。

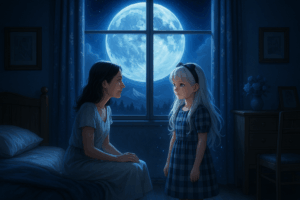
コメント