二人は静かに実家へ戻った。
庭のベンチは、かつてスーが日向ぼっこをするのが、お気に入りだった場所。
今は満月の光がやさしく庭を照らしている。
青白く揺れる木々の葉、蒼い光をまとうゼラニウムの花々。
二人は並んでベンチに腰を下ろし、私は空を見上げた。
スーと過ごす時間は、あまりにも穏やかで、幸せで——
だからこそ現実へ戻ることが、終わりが近づくのが、とても怖いと感じる。
表情を曇らせる様子に気づいたスーが、心配そうに顔をのぞき込んできた。
「……ねえ。膝枕、してあげよっか?」
私は小さく笑って頷いた。
「……うん。お願い」
ベンチに横たわると、スーの小さな膝に頭を乗せた。
白い髪がさらさらと頬に触れ、ほのかなぬくもりが心に沁みる。
「このままずっと、スーと一緒にいたい」
声が、かすかに震えていた。
「元の世界じゃ、うまくいかないことばっかりで……
まわりに迷惑かけてさ。もう、どうしていいか分かんなくなってる」
スーは黙って、言葉に耳を傾けていた。
「好きだった絵も、最近は、描くのが、こわくなっちゃった。
描けば描くほど、自分のダメなところばっかりが見えてくるみたいで」
声は掠れ、涙の気配がにじむ。
本当は、こんなことスーに言いたくなかった。心配をかけたくなかった。
でも、こぼれ出てしまう。
「……そっかぁ」
スーは静かに呟いたあと、しばらくの間、何も言わずに私の髪を撫でていた。
「絵を描くの、好きだったもんね。わたしの絵も描いてくれたことあったよ。
……最初は、なにが描いてあるのかわかんなかったけど」
そう思い出すように言って、クスッと笑った。
「……ごめんね。難しいことは、よくわかんない。でもね」
夜空を見上げながら、やさしく言葉を紡いだ。
「セナの世界は、こんなにキレイで素敵なんだよ。
なのに描かないなんて、もったいないと思うけどなぁ」
「え……?」
「だって、見てよ」
私は顔を上げ、まわりを見渡した。
そこには、幻想の庭と蒼い満月の光が広がっている。
(そうだ……ここは、『思い出づる国』。わたしの願いが形になった世界)
勢いよく起き上がり、辺りの景色を見回す。
視界いっぱいに広がる夢のような光景。
ここに来たとき、不思議と既視感があったのは、ただ故郷の土地だったからじゃない。
この町も、この空も、この色も——
自分の心の中にあった景色が、まるごと世界になったんだ。
スーは、不思議そうに首を傾げる。
「どうしたの、急に?」
その仕草に、思わず笑みをこぼした。
「これは、わたしが描いた世界…… ううん、違う」
そう、違う。この世界は、わたしだけが描いた世界じゃない。
スーの手を取り、しっかりと握った。
「これは、わたしたちの世界だよ。だから、こんなにきれいなんだ」
胸の奥から、自然に言葉がこぼれた。
この景色が美しく映るのは、私が“スーと過ごした日々”を、心の底から愛おしんできたから――。
笑い合った時間も、泣きそうになった夜も、そのすべての想いが、この世界に色を与え、温もりを灯してくれている。
ふと、初めてスーの絵を描いた日の衝動がよみがえった。
たまらなく愛しくて、どうしても、この手で彼女を残したいと願った。
私が絵を描く理由は、あふれる想いを色と形に変え、誰かの心へ届けるため。
そして、そのきっかけをくれたのは――間違いなく、スーだ。
「私が絵を描くことを好きになれたのは、スーのおかげだよ」
ふっと笑って、言葉を続ける。
「だから、負担に思ったことなんて、ないんだから」
スーは息を呑み、何かを探すように私の顔をじっと見つめてくる。
「……ほんとに?」
震えるような声。
私は小さくうなずき、まっすぐ視線を返す。
「ほんとだよ。スーの全部が、大切だった」
しばしの沈黙。
やがて、スーの瞳に光が滲み、息を詰めたまま小さく笑った。
「そうなんだ……。そうだと、うれしい……」
その笑みは、長いあいだ胸の奥に閉じ込めていた不安を、ようやく手放せたようにやわらかかった。
その時——
握っていたはずのスーの手が、ふっと、手の中から抜け落ちた。
「あれ……?」
私は思わず手を伸ばした。
けれど、そこにはもう、触れられる温もりはない。
空を見上げると、蒼く輝いていた満月は、もう山の向こうへ沈みかけていた。
——別れのときだ。
まだ、言いたいこと、伝えたいことがあったのに。
それでも、時間は待ってくれない。
目の前にいるはずのスーの姿が、少しずつ遠のいていく。
「セナ……」
スーも困惑した様子で必死に手を伸ばしているが、互いの手は無常にも触れられない。
「スーっ!」
駆け出した――が、足は地を踏みしめる感覚を失い、空を掴むように進まない。
「スー! 待って! まだ……まだ大事なこと、言ってない!」
一瞬の静寂。
胸が締め付けられ、喉が固まって、言葉がうまく出てこない。
「ずっと一緒にいてくれて、ありがとう!」
振り絞った声が響き、涙でにじむ視界の中で、スーの瞳が揺れる。
「……最後に会えなくて、ごめんね」
涙に震えた、その声に応えるように、スーは瞳に大粒の涙をたたえながら——
それでも、優しく微笑んだ。
「わたしも、セナと一緒にいられて、本当によかった。
たくさん愛してくれて……幸せだったよ!」
頬を伝う涙は、光の粒となって空へ舞い上がっていく。
けれど、二人の顔には、笑顔が浮かんでいた。
ずっと言葉にできなかった想い。
最後に伝えたかった後悔と感謝。
それらすべてが、確かに二人の心に届いた。
離れていく距離は、もう止められない。
でも、もう、寂しくはなかった。
「バイバイ、セナ。——だいすき!」
「私も。だいすきだよ、スー!」
光が消える直前、最後の一瞬——
スーはやさしい微笑みのまま、月光に洗われるように消えていった。
町の色も空の光も、静かに幕を下ろしていく。
そして、すべてが静まり返った。
気づけば、自室のベッドの上に、ぽつりとひとりで座っていた。
窓の外には、もう満月はなかった。
けれど——
頬には、確かに温かい涙の跡が残っていた。

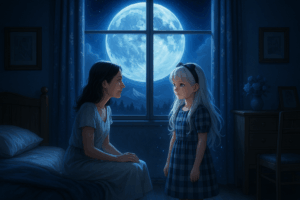
コメント